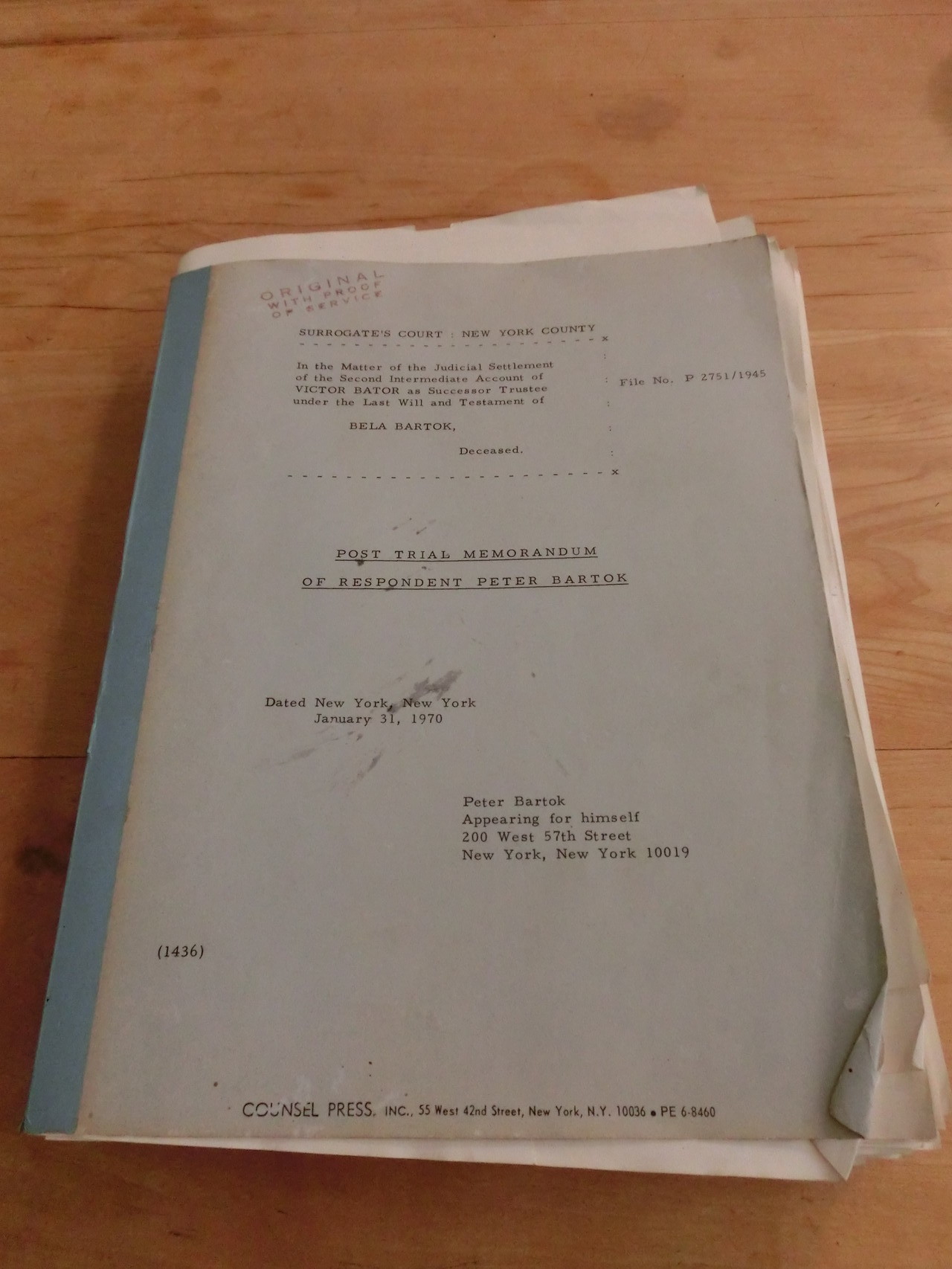2014年 ペーテル宅滞在
2013年に『父・バルトーク』の完成報告のために訪問してから1年。2年連続という贅沢には多少躊躇しましたが、90歳という大きな節目は外せませんでした。
ペーテル90歳のバースデー・ディナー

前年と同様に、ペーテルの誕生日の7月30日に合わせて訪問し、その晩、90歳を祝うディナーに出席しました。場所はペーテルの自宅から北に車で10分ほどのヴィンテージ・オン・フィフス、私にとっては2度めの来店でした。
全員で8人、私以外はバルトーク・レコーズのスタッフとその家族です。私も仲間に入れていただけて、これほど光栄なことはありません。
ペーテルは子ども時代の夏休みをエルザ(ベーラ・バルトークの妹)の家で過ごし、アメリカの夏は農場や軍隊にいたりして、誕生日を両親と共に過ごすことがほとんどできませませんでした。それだけに私はお誕生日を大事にしたかったのです。私事ながら、学校教員として吹奏楽部顧問を続けていたらこの時期はコンクールの県大会と重なって渡米できませんでした。
今回、スイッチを入れると「バルトーク・レコーズ」のロゴが浮き出て光る照明器具をバースデイ・プレゼントとして用意しました。かつての教え子が製作してくれたものです。道中の破損や盗難に備え、手荷物検査や税関が気にしながら、日本からリュックサックで背負って運びました。
レストランに30分ほど早く着き、リハーサルに抜かりはありません。夕方新しく買ったテーブルタップが部屋のコンセントからペーテルの席までちょうどの長さで安堵したのも束の間、電源を入れても器具が光りません。前夜に到着してすぐに器具は動作確認してありました。別のコンセントで試そうと、廊下のコンセントに接続されていたランプのプラグを抜こうとしたら
店員「お部屋のコンセントは故障中です。ここはお客様が通るのでご遠慮ください」
私 「30秒でいいんです。光るのを見せるだけですから」
店員「どうかご勘弁を…」
電源の故障を放置しているのにはあきれるし、客に対する共感のない対応にも失望しましたが、おめでたい集まりの前にトラブルは避けようと思って引き下がりました。食後のケーキの時間、光らない照明器具を披露するに留まり、正式なお披露目は翌日に延期されました。残念…。
翌日あらためてバースデー・プレゼントを披露

翌朝、あらためて誕生日プレゼントを披露しました。電源を入れると、ほぼ透明だったアクリル板のロゴだけが白く光ります。バルトーク・レコーズの玄関に飾っていただきました。以前から書斎のデスクにあった「バルトップ・レコード」というパロディの赤いプレートまで並べてくれましたが、それはデスクに置いたほうがいいですよ。
発見! ベーラ・バルトークの絶筆

今回、大きな発見がありました。《ピアノ協奏曲第3番》の末尾にあるベーラ・バルトークの絶筆です。
父は弱っていて議論を続けられず、救急車がすぐ迎えに来ることで話がついた。(略)私にもスコアの2ページに縦線を引くように頼んだ。指示は17小節*
だった。私が定規を当てて線を引き終えると父は小節数を数え、正しいことを確認すると最後の小節線にもう1本書き加え、「Vége(完)」と記入した。(『父・バルトーク』177-78ページ)
*『父・バルトーク』のこの箇所の「17ページ」は誤りで、正しくは「17小節」です。お詫びして訂正いたします。
この本に掲載されているのは、本文とは異なり《ピアノ協奏曲第3番》のスケッチの写真です。日本のみならず欧米の出版物でも、フルスコアの写真は見たことがありません。
7月31日、ペーテルにお願いすると、フルスコアのコピーを2冊見せてくれました。ところが、最後のページに肝心の「Vége」の文字がありません(写真) 。問題はそれだけではありませんでした。手稿譜の最後の17小節間とそれ以前とでは筆跡が一致して見え、シェルリが補筆したとは思えないのです。

「どういうこと?」ピーター・ヘニングス氏も加わり、3人で考え込みました。ペーテルはこのエピソードの「証拠」を示すことに興味がなかったのか、気づいていなかったようです。結局、未解決のままこの日は時間切れになり、ペーテルのバースデー・ディナーに向かいました。
翌8月1日の午前。くつろいでいると、ピーターが別のコピー** を探してきてくれました。その最後のページを開くと、そこには確かに「vége」の文字が!(写真) どうやら昨日の2冊は、鉛筆の文字が薄いためにコピーされなかったのでしょう。バルトークが五線紙に最後に書きとめた文字が、69年の時を経て公開されました。
**バルトークの本物の手稿譜は、将来に備えて数年前にヨーロッパの安全な施設に移しました。その所在は時が来たらお知らせしましょう。現在、ペーテルの手元にあるのは手稿譜の写真コピーです。ただし、書簡や初版楽譜、写真や書類等は本物を保管しています。

それでも2つめの疑問はまだ解決していません。最後の17小節間はそれ以前と同一人物が書いたように見える点です。例えば《青ひげ公の城》のスコアには妻のマールタによる写本がありますが、これらも他者による写本のコピーでしょうか? それにしてはバルトークの筆跡とあまりによく似ています。音符も文字も、そしてペンやインクまで…。
手稿譜コピーを精査した結果、謎はおそらく解けました。なんとティボル・シェルリがバルトークの音符や文字の書き方までそっくりに書き、その結果、曲全体がバルトークの筆のように見えたのでした。本来はバルトークとは別の五線紙に…という判断も考えられますが、シェルリのバルトークに対する尊敬や憧憬によるものでしょう。
手稿譜のコピーをいただかなかったので、販売スコアでバルトークからシェルリのオーケストレーションに切り替わる箇所を、太い縦線で示します(写真)。実際はそこでめくりになっていて、最後の17小節は五線紙で2ページ分あり、各ページとも各段の左に省略楽器名が記されています。シェルリはその文字の筆跡までそっくりに書きましたが、微細なトメ・ハネの点でバルトークの筆跡とわずかに違う文字が見つかり、それが解決の手掛かりとなりました。
ところで、バルトークからシェルリの筆に切り替わる五線紙のページめくりに、小さなギャップができました。
まず、2部に分かれていたバスーンがめくりの後でD音の単音になります(写真、上の四角)。バルトークなら音符の上と下に符尾を書いたでしょうが、ここの符尾は1本になっています。進行上「a 2」(2人で)を意味するものと想像でき、音に影響はありません。
影響という点で目を引くのは、チェロの進行に「A→D」という11度の不自然な跳躍ができたことです(写真、下の四角)。スケッチ*** で低旋律は「F#→B→E→A→D」と4度ずつ上行しています。バルトークはスコアリングの際にテューバとコントラバスは4度上行させつつも、チェロだけは「E→A」の箇所で5度下げました。これは音域が上がり過ぎるのを避けるためで、次のページでチェロは4度上行を再開するつもりだったと思われます。しかし、シェルリはスケッチを尊重してチェロに高いD音を与え、結果的に11度の跳躍ができました。以上は仮説ですが、私はチェロのD音は出版楽譜より1オクターヴ低い、テューバやコントラバスと同音が正しいと考えるに至りました。
*** スケッチの該当箇所は『父・バルトーク』177ページに掲載。
いつものベランダでくつろぐ

バルトーク・レコーズの玄関前のベランダです。ペーテルはここで庭を見ながらゆっくりとコーヒーを飲んでいます。野生のリスやカメがやってくる時もあります。空気はフロリダらしく温かく湿っていて、夏場は短時間のスコールが降ることもあります。私は2度めの滞在以来、ここでペーテルの話を聞いています。多くは『父・バルトーク』で述べられたことの繰り返しで、時には今後の計画などもあります。
バーベキューに

8月1日の昼は、ピーター・ヘニングスさんが上記のベランダの隅で、バーベキュー風にステーキを焼いてくれました。ペーテルが横から焼け具合をのぞき込んでいます(笑) さすがアメリカで厚さ2cmほどのステーキ用ビーフが手に入るんですね。お昼はこの贅沢なステーキとポテトで大満足でした。
 Bartók Records Japan
Bartók Records Japan